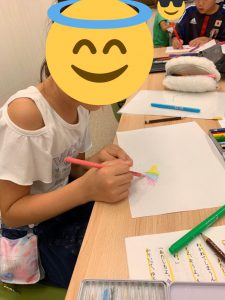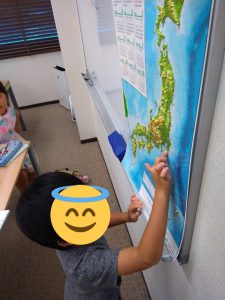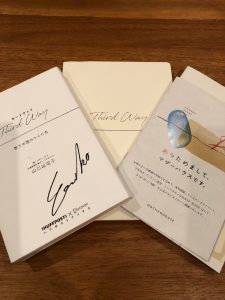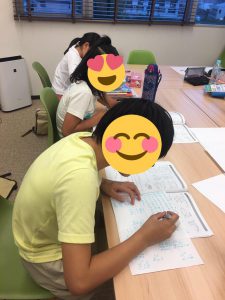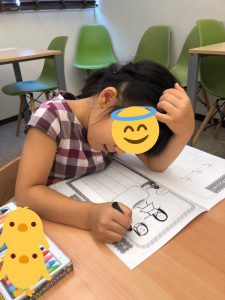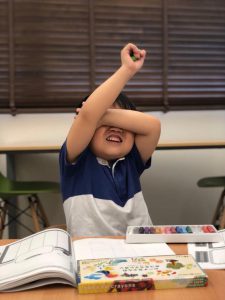先日、授業終わりにお迎えにいらっしゃったお父さまとお話したときのこと。
もう教室に4年以上通ってくれていて、いつも笑顔。勉強以外のことにもたくさんチャレンジし、実力だめしに受けに行った模試の成績などもすごくよかったりする子なのですが、
「いっつも遊びに行ってるみたいなんですがうちの子って勉強してます!?」
といわれました。
たしかに、世間話をするように教室にきて(いつも「あんな〜今日な〜」と報告を受けています)、授業中はむずかしいことをやってはいるけどどんどん質問をしながら取り組み、ツッコミをいれ(言葉の発達により年々鋭さを増してきています)終わった後もみんなを巻き込んで遊び、時間になったら「じゃあね〜」と帰っていく。
先生たちみんなが、「こんな風になってもらえたらいいよね」と思ってやっていることを見事に体現してくれている子だねといっている子ですが、客観的に見ると、遊んでいるようにも見えるのかなと思いました。
でも、社会で活躍する子、リーダーになるような人って、眉間にしわを寄せてがんばっているというよりも、それが好きで楽しんでやり続けているうちに影響力を持ち、まわりを巻き込んでいっているような人なのですよね。
「頭のいい子」というと、どんな子を思い浮かべますか?
集中力が高く、やるべきことをさっと終わらせられる子
優先順位をつけるのが上手で、必要なこととそうでないことを見分けられる子
パッと解決策やアイデアが浮かぶ子
計算や決断が早い子……
じつは、これらはぜんぶ「ワーキングメモリ」という能力によるもの。
「IQ」を賢さだと思われている方もいますが、IQはあくまで「知っていること」。
お金をかけ、いろんなことをやれば伸ばすことができたりします。そして、将来の成功にはほとんど相関性はないということがわかっており、情報自体は探せば見つかる21世紀の将来の成功を測る物差しとしては最適ではない、とアメリカの心理学者などもはっきりと言っています。
21世紀型の賢さ、「知識を使って何かを生み出す」というのは「ワーキングメモリ」のやることなのですね。
ワーキングメモリの強さにより成績を95%の確率で予測できるという研究もあります。
低学年のクラスだと、とくに「ワーキングメモリの強化」というのを大きな目的のひとつとしてやっていますが、それらが育っているのをみると、これからどんな風になっていくのかなと楽しみにさせてもらっています。
低学年〜中学年のホップクラスを長くやっている子の中には、すごく明るくなったなと感じる子もいますが、ワーキングメモリには感情の切り替えがうまくなり、楽観的になりやすくなる、という研究も。
こんなすごいことだらけのワーキングメモリ。鍛えない手はありません。
お家でも、
・充分な睡眠(10〜11時間を目安)
・ 毎日の読み聞かせや音読、読書
・ 歩く、走るなどの運動
・ 数独などのパズル
・ ゴールから逆算して考える
・ メモをとる
・ 部屋や机の整理整頓をする
などで鍛えることができます。
ぜひ、やってみてくださいね^ ^