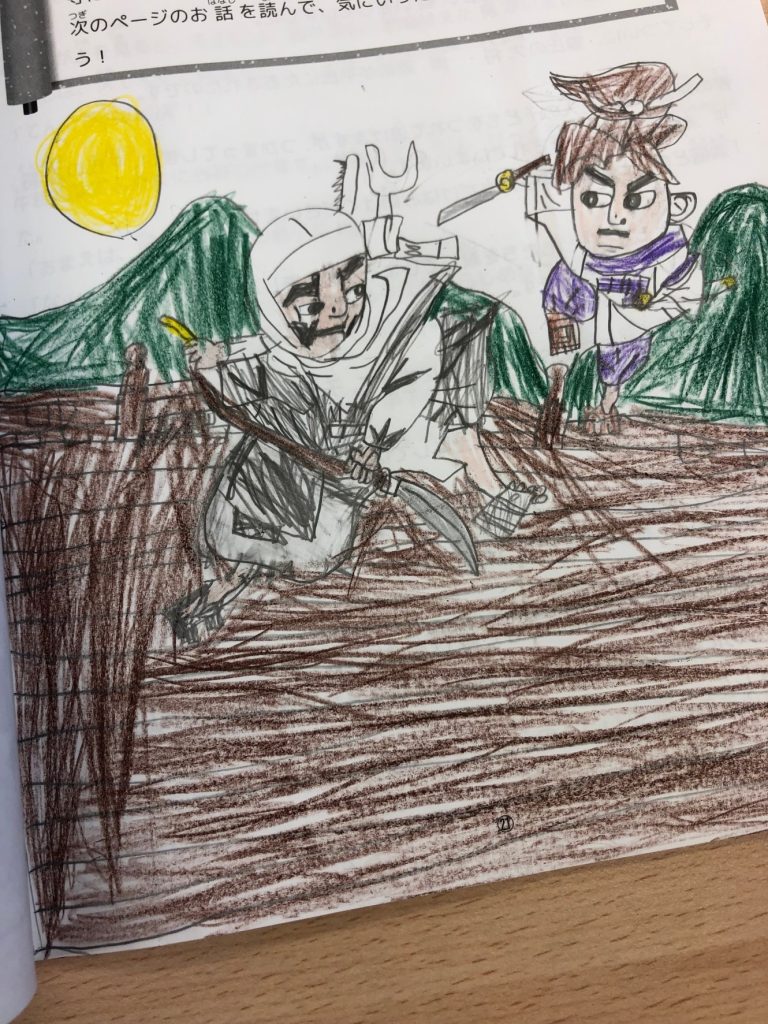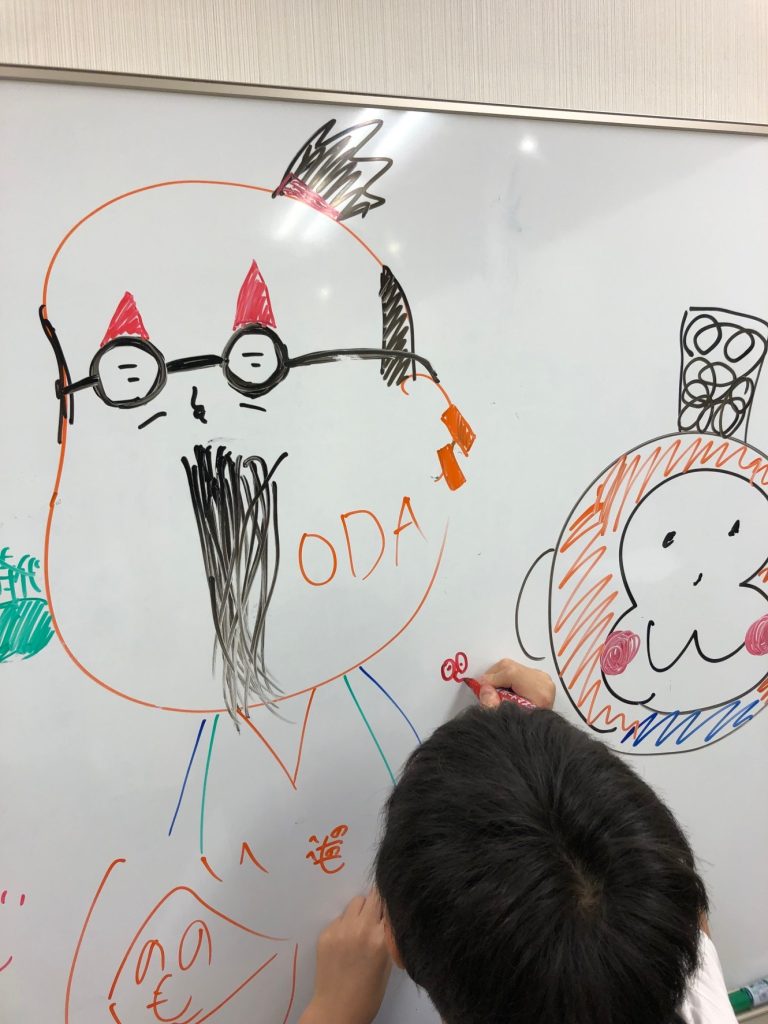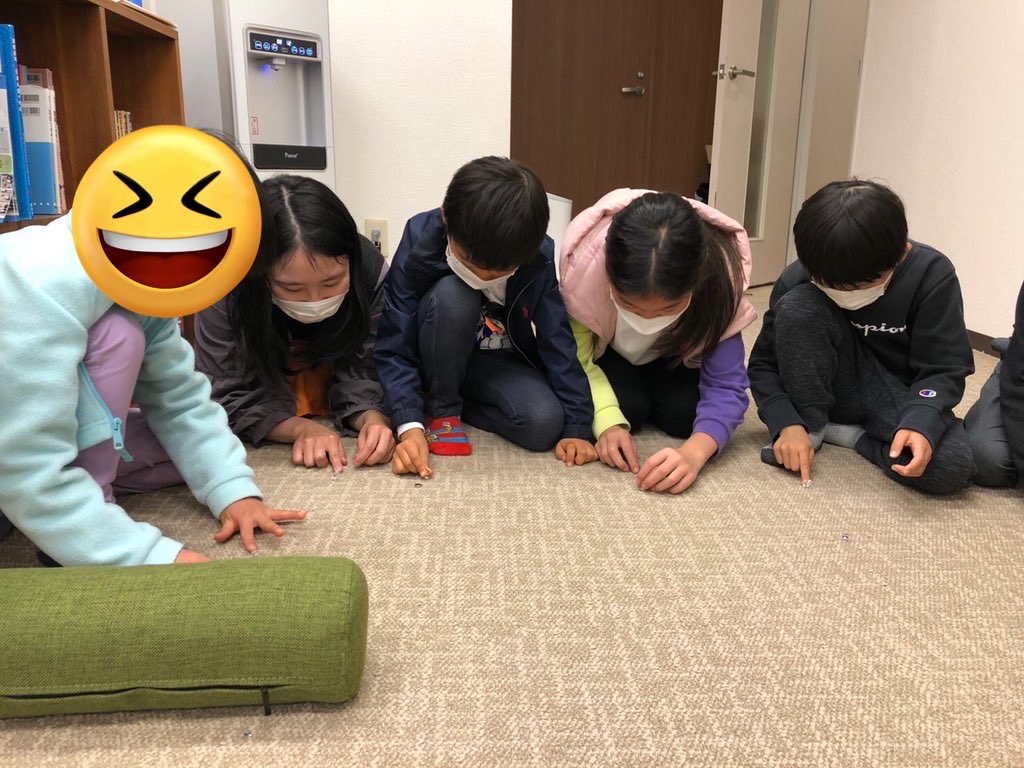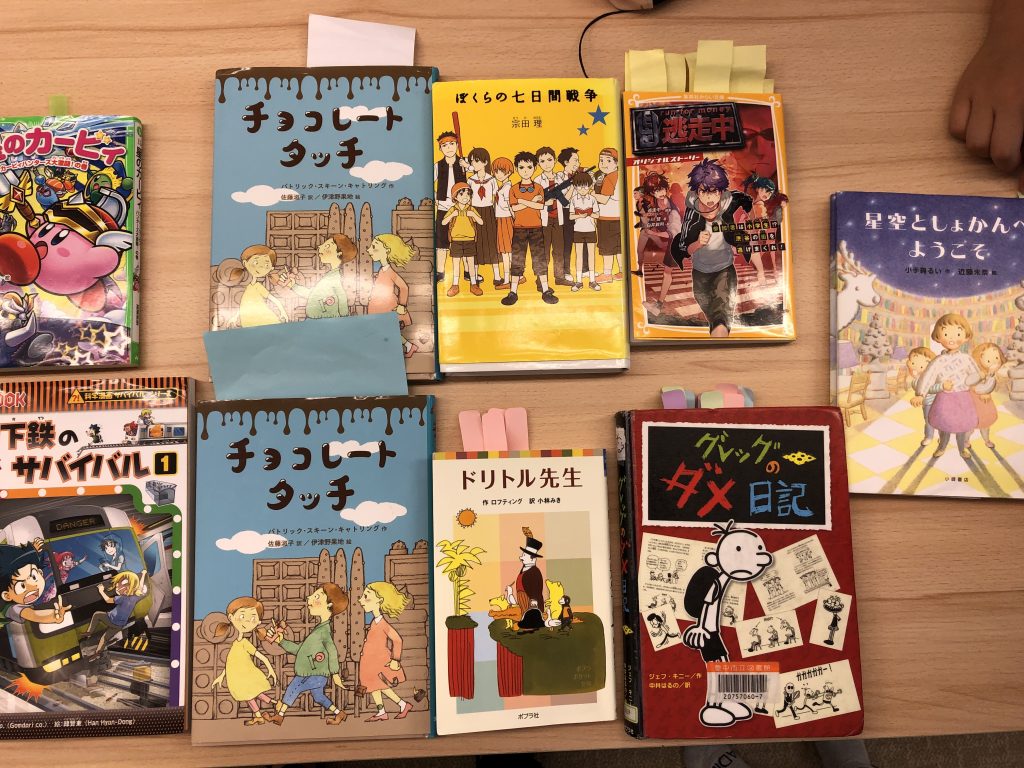こんにちは。
新留です。
以前のこと。
3年生の男の子たちから、
「先生、今から言う『ことわざ』答えて!」
と問題を出されました。
どうやら、家でたくさん「ことわざ」の本を読んで、覚えてきてくれたようです。
ステップクラスからは、「言葉のテスト」というのが始まりますが、
子どもたちの中には、それをきっかけに言葉への興味が湧き、
メキメキと語彙力をつけていっている子がいて、
授業中も、
「それって、〜ってことわざと似てる!」
「それは四字熟語でいうと、〜だね!」
なんて感じで、どんどん覚えたことを発表してくれています。
ステップクラスは3〜6年生の子たちがいて、
意識的に、言葉を深く、つなげて覚えていく練習をしていきますが、
早速、子どもたちの中に、言葉に関する興味、関心が芽生えて、
言葉に対する感度が上がっていっているのを感じ、うれしかったです^^
先日も、保護者さまから、
「読解力をつけてほしいと言っているお友達がいたので、RAKUTOを紹介しときました!」
という連絡をいただいたのですが(ご紹介ありがとうございます!)、
いちばん大事にしている「国語力」、「読解力」で選んでいただけているのは僕らとしてもうれしく思います。
「どうやったら、読解力をつけられますか?」
というご質問をいただくことが多いですが、
「読解力」をつける際、
まず、チェックしてほしいのが「語彙力」です。
「読む」の前に、まず、「言葉」、「単語」があるのですよね。
シカゴ大学の教授であったM.J.アドラーの『本を読む本』という名著がありますが、
その中で、アドラーは読書の第一レベルは「単語の識別」だと書いているように、
「単語」がわからないと、そもそも、「その文が何を述べているのか」がわかりません。
時々、子どもたちに、文章の単語部分を真っ黒にして、
「単語の意味がわからないってことは、こういうことなんだよ〜。単語の意味がわからないと、たとえ、文章を『文字として』読めていたとしても、意味がわからないんだよ」
ということを説明するのですが、
まず、「国語が苦手」、「読解力がない」という場合、
「語彙力がどうか?」
というのをチェックし、身につくようにしていってもらえたらと思います。
「音読が苦手」というのも、「語彙力」の問題の時が多いです。
「単語の区切りがわからないから変なとこで区切ってしまう」、
「単語が難しいから注意がそれてしまう」のですよね。
知らない単語だらけの英文を見たら、読む気がなくなってしまうのといっしょです(笑)
まずは毎日の生活の中、会話の中で、
たくさんの言葉に触れられるように、
そして、それも平面的にではなく、類義語、対義語なども一緒に知り、立体的にいろんな角度から、
漫画やイラストなどを見て、視覚的に触れていってみてくださいね^^