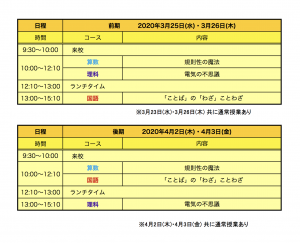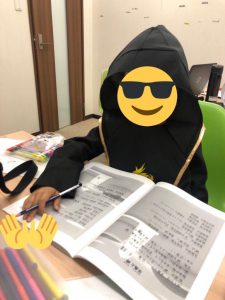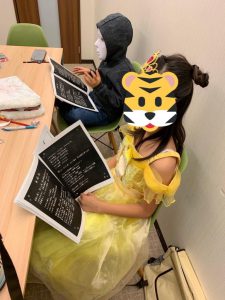こんにちは。
新留です。
先日、箕面の滝道を少し上がったところにある「明治の森 箕面 音羽山荘」にお世話になっている先生にご飯に連れていっていただきました。
音羽山荘さんといえばお食事だけでなく、旅館としてや結婚式場としても利用される大正15年築という由緒あるお店。
お昼から一品一品手の込んだ料理とともにとても優雅な時間を過ごさせていただきました。
コース料理が始まり少し経った頃、部屋の担当だった仲居さんが、
「こちらよかったらお土産に持ってお帰りくださいね」
と箕面ビールの蓋をきれいに袋詰めしてくださったものをプレゼントしてくださいました。
そして、料理の終盤にはサプライズで誕生日のデザートプレートまで出していただき、
(基本的に自分の誕生日や年齢をあまり覚えていないので「ハッピバースデートゥーユー」の歌を歌われたときに最初、誰が?と思ってしまいました……一昨年は自分の年齢を1歳上に間違っていたりと意識の低さが目立ちます……)
ご飯の後には、宿泊や結婚式もできるお屋敷内を案内してくれたり、箕面の歴史をお聞かせくださるなど、風流を感じるとても素敵な時間でした。
昼食後、教室に戻り、授業の準備をしていると、音羽山荘でいっしょに昼食を食べていた6年ほど箕面校で働いてくれているスタッフひびちゃんが、
「これ、プレゼントです」
と袋をくれました。
「おおーっ、ありがとう!」
とありがたくプレゼントをもらい、袋の中を見ると、
そこには選んでくれたプレゼントといっしょに、つい数時間前に、仲居さんが心を込めて、きれいに袋詰めまでして1人ひとつくださった箕面ビールの瓶の蓋が……
仲居さんの好意……
昔々、好きではない男性からのプレゼントをすぐに質屋に売る女子大生などがいるという話をテレビで見たことがありますが、こういう女性のことなのか……と衝撃を受けました。
さて、スタッフひびちゃん本人は「いらなかったから捨てたわけではなく、間違えて入れてしまっていた」と弁明をしていましたが、相手に伝わる愛情表現の形ってあるんですよね。
保護者さまから、
「子どもには褒めたり、ハグをしたり、愛情をいっぱい注いできたはずなのですが、どうも、あまり伝わっていないみたいで……」
というご相談を受けることがありますが、そのお話を聞いていると、子どもが愛情を感じる形と、保護者さまが愛情だと思ってやっていることにズレがあるときがあります。
保護者さまが愛情表現だと思ってやっていることは、自分がされたらうれしいことだったり、自分がされてきた形だったりしますが、それが子どもの愛情を感じる形ではなかったりします。
(僕も、誕生日に「貴方を想って彫りました」と木彫りの人形をもらっても困ります。純金だと喜びますが)
兄妹などで多かったりしますが、受け取りやすい形が違っていたりすることって多いんですよね。
「同じように愛情を注いでいるはずなのに、どうも愛情が伝わっていない……」
そんなときは、どうされたらうれしいのかな? とちょっと子どもが喜んでいる時や嬉しそうな時を観察してみてください。
「ほめられたり、認められたりしたらうれしいのか?」
「2人きりでゆっくりする時間をつくってあげたらうれしいのか?」
「いっしょに遊んだり、ハグをしてあげたらうれしいのか?」
「何かプレゼントや、ちょっとしたご褒美をあげたらうれしいのか?」
「何か子どもがやりたいことや目指していることをサポートしてあげるとうれしいのか?」
いろんな形を試してみてくださいね。
子どもへの愛情がしっかりと伝わりますように。